【画壇・風雲時代】
後世、この一時期を指して示される呼称である。
風雲と冠されてはいるものの、戦国時代の動乱のような剣戟・口論舌禍の類ではない。
絵筆とキャンバスを武器とし、己が世界観を世に提示せしめんとする情熱の萌芽である。
が、絵師たちの静かなる渦は、互いの向上心と敬意を中心に、大きく力強く螺旋を巻いていた。
【A-Z】、【矢塚一夜】、【安東敏也】、【ロックハウンド】
有名無名を問わず、絵を展示した者の名前は、確かな足跡として刻まれる。
モチベーションとインスピレーションの導く先に、確かなテクニックを求め、日々研鑽を重ねていくのである。
彼らを受け入れ、また新たなる来訪者・挑戦者の舞台として、惜しみなくその場を提供する美術館が、今日では3箇所を数えた。
新作の仕入れは活発ながら、展示が遅い事で知られる【登山道】。館長の紫苑氏は「M=)忙しくってつい…」との言い訳が有名である。
そして「狐画廊」の異名を持ち、ことに合作の充実が目を引く逢川館長の【TAF美術館】は、館長自らの作品も展示されている名所として知られる。
そして西洋風の喫茶店(カフェ)であるにもかかわらず、館(ハウス)を想わせる重厚な造りと、鑑定眼・品評の厳格さ。そして、何時からか学芸員(キュレーター)と呼ばれ出した店員たちにより運営されている【ストーリー・アヴェニュー・カフェ(Story Avenue Cafe)】。
以上の画廊を3基点とし、展示された作品群は比類なき名品揃いであり、作者陣もまた日本画界の一角を担うに相応しい力量を示している。斯様なる現状の日本画壇において、若き天才の一人として、綺羅星の如く現れた幾人もの俊英達と肩を並べ注目されている人物こそが【はっかい。】なのである。
アトリエ・エイト・シーズ!
〜光と影の天使たち〜
以上の3箇所に、【はっかい。】画伯の画廊を加えて4箇所となる。
パリの『カフェ・ドゥ・マゴ』、あるいは中世におけるサロンのように、新進気鋭の若き芸術家たちの集う場所として、客足は進んでいた。
また画家陣も暇さえあればアトリエに足を運び、思い思いにひと時を過ごすのである。
新旧の芸術談義を交わし、文士の知己あれば、文筆との交流を図り、時には合作・競作の約定を交わす。
「ろりっこししょーのA-Zさま。水無月のプロポーズを受けてほしいですの」
「だが、断る」
極く一部の悲喜劇はさておいて、押し並べて芸術の協調関係は睦まじいものであった。
日々新たなる創作の種は蒔かれ、芽生えと収穫を繰り返す。
はっかい。もまた、創作家の1人として携わっていた。
【アトリエ・エイト・シーズ(Eight Seas)】というのが、住宅兼工房の名称である。都内近郊の住宅地、小高い丘の上に佇む、とある古式ゆかしい西洋風の木造二階建てアトリエ。その住人にして主たるはっかい。が、都会の喧騒を離れた理由を聞かれれば、このほぼ隠遁生活に等しいうら寂しさを、むしろ好んで、現在の生活を選択したというのが友人間での定説であった。
人間嫌いというわけではなかった。『夜咲華』芸術新人賞・受賞式典での席上にて、見出された朗らかな社交性には、芸術家にありがちな世間性の欠如と傍若無人な態度が、はっかい。とは無縁のものであることの証左である。自他共に認めるところは美点として受け止められており、それ自体は悪いことではない。が、ともすれば彼自身の認識以上に世間の目が彼に注がれてしまう、という結果をこそ、彼は疎んじていたのかもしれなかった。
知る人ぞ知る、ということは、裏を返せば知らない者は知らないわけであり、メディアを通さずして、一般大衆の認知に至る事は無い。逆を言えば、情報そのものの秘匿性を軽んじてしまう一面があるわけだが、秘すれば花の例え通り、秘密であればこそ神秘性も加味され、対象のミステリアスさを存分に醸し出す事が出来るのである。
だが、ごくまれに、秘そうが秘すまいが、その神秘性と対象とがイコールで結ばれてしまうことがある。
すなわち対象そのものが神秘的ということであり、すでに人口を膾炙していたそれは、明らかなる事実として、衆目を惹きつけずには置かない磁力を発生させていた。
故にティーンからヤング、はては映画や写真、週刊誌等々の芸術系以外からの取材依頼が月に300件を超えたのは、ひとえに彼自身の容貌にあった。
はっかい。は、恐るべき『美形』であったのである。
―――AM9:38
擦りガラスの窓を透かして、陽光が差し込んでくる。
春の夜露を着飾ったものか、艶めく薄靄がアトリエ内にも香木の煙のように入り込んでいた。
「詰まる所、芸術とは技術の集積と霊感との調和だね。そのワン・センテンスで語は足りる。言い換えれば、それで理解し、表現し得ぬ奴は見込みが無いのさ。デッサン以前に鉛筆の握り方から始めるべきだ。そう思わないかい、ぼまー?」
「良く分かりませんですの」
入れたての紅茶の香りも漂う中、デッキチェアーに腰を下ろし、馥郁たる色と渋みを楽しんでいるのは【はっかい。】とその教え子たる【水無月】である。弟子といっても水無月の一方的な自称であり、はっかいにしてみれば、朋友であるA-Zに体良く押し付けられた話し相手以外の何者でもなかった。傍目には長年付き合いの旧友同士にしか見えないのだが、そこがまたはっかいには癪に障ることであった。
「つまるところ、才能は努力なくして育つことはなく、努力もまた才能の芽生えなくしては、その伸ばす先が見えない。種を植えていない畑に水をやるようなものさ。自分が育てたいと願う才能を見つけ、そして育てる。その際に計画性という戦略と、周囲の環境と天候をそれとなく読み取る感性、すなわち霊感が必要だというのさ。わかるかい?」
「つまり、天才には天才に、バカにはバカにだけ出来ることがある、ということですの」
一杯目の紅茶をあっさり飲み干していた水無月は、蜂蜜入りのミルク・シェイクで更に咽喉を潤す。
滑らかになったらしい口は、『お花畑に花が咲きましてよ』と言わんばかりに明るくも軽やかな口調で、毒を吐き出していた。
聞かされたはっかい。は噎せて、せっかくの紅茶を吐き出してしまっていた。
「ああ、なんてことだ。極論的ではあるがあながち外れちゃいない。しかしひどい言い草だ。それでいて僕が教えたはずの手腕を放棄してくれるのだから全く始末に困る。これだから君には講義のし甲斐が無いと言うのだ、ぼまー。この爆弾頭」
「光栄ですの、ハチ姉」
秀麗なはっかい。の表情がしかめられた。
梅干しの酢漬け、果肉ステーキのパプリカ&タバスコ添えを一気食いしたかのような渋面である。
それでも損なわれない美貌があるのだから、見た者があれば、神の不公平を呪いたくなったであろうが。
「何度言えばわかる。僕を【ハチ姉】と呼ぶな」
「だって【ハチ姉】は【ハチ姉】ですの。皆、噂してますの。あんな美形見た事ない。長い髪の毛のお手入れ、どうやってるのかしらって」
「きちんと風呂に入っていれば誰でもこうなる! 世の中、忙しさにかまけて、自らの容貌を客観視することがどれほど大切か、皆、わかっていないのだ。最低ランクである臭気や衣服にすら気を留めないなんて信じられない。酸っぱい体臭なんか嗅いでしまった日には、僕は気が狂いそうだよ」
緑の黒髪、鴉の濡れ羽色。
様々な形容詞をもって称される美的要素を、はっかい。が持ち合わせていた事がこの際は彼にとっての不幸であった。
容姿をとやかく言われるのは気に入らないが、生まれ持ったものを大事にしないのも、はっかいは腹に据えかねた。
芸術家としての品評眼・価値観がそう思わせるのか、余人に対してもそうである。
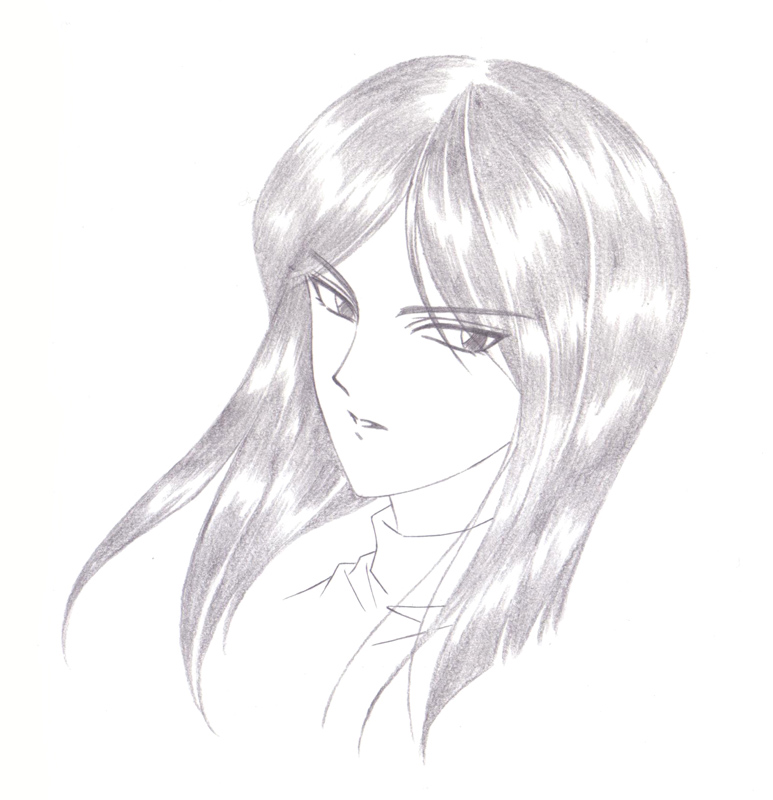
憤りも束の間、からん、と来客を告げるドアのカウベルが鳴った。
仕立てはイギリスの生地であろうか、淡いトーン柄が基調となったスーツがかっちりと着こなされ、一見して大学の女性講師を思わせる女性が、静かにドアを潜ってくる。
ことりことり、と革靴の底が板張りのアトリエを鳴らし、リズムに品格を添えた。
「やぁ、お邪魔するよ、レジェンド」
「来たな、A-Z様。この諸悪の根源め」
やつあたりの気分を多々に込め、はっかい。が挨拶を送る。
言葉を投げかけた先には、同じく新進気鋭の画家として名を馳せるA-Zが居た。
伝説級の絵師という賛辞をこめて、はっかい。に対しA-Zは『レジェンド』という呼称を用いている。
『これでA-Zは引退できる』が口癖だが、誰もが端っから戯言かつ信用度ゼロ発言としか認識していないので、もっぱらスルーという名の無視扱いとなっている。
「藪から棒に酷い事を言うなぁ、レジェンド。レディー・ピュアネスこと良心の天使とはボクの事だよ」

「よく言うよ。君のおかげで僕のアトリエは静謐と調和からかけ離れた、喜劇専門の劇場と化してしまった。どうしてくれる、A-Z様?」
知的な美人という外見のA-Zに対し、口調こそ穏やかなものの、視線も態度もどこか剣呑である。
子供が拗ねている、というには年を取りすぎているが、女性であれば溜息を漏らさずには居れぬ美の前では、顰められた眉ですらも賛美の対象なのであった。
「前々から言っているじゃないか。もういい加減に猫の皮をかぶるのはよしたまえと」
「不愉快なテーマソングを送られて、黙って享受している僕だと思うのかい、A-Z様? もっとも笑わせてはもらったが」
音楽にも造詣の深いA-Zは、その才能を遺憾無く発揮し、過日、『八休さん』というタイトルの歌をはっかい。に捧げていた。
「真実だよ。『ERO絵は鮮やかだよ一級品 』。まさにレジェンドこと【はっかい。】画伯の真実じゃないか、あっはっは」
「業腹だが認めよう。だけどその後が悪い! なぜ『だけどほのぼの偽者だよ八級品』なんだ。ほのぼのを描いたら偽者扱いされるとはどういうことなんだ。ほのぼのな僕は偽物だと言うのか。EROを描かなければ僕は僕でないとでも言うのか!?」
「うん」
「あっさり!?」
女性ばっかり描いてきたのが不味かったかもしれない。
はっかい。は今更ながらに悔いた。だが悔やんでも仕方の無い事ではないか。問いを投げかけてくる自分の声を感じる。
確かに女性は好きだ。なんだかんだ言っても『エロース』を描いてしまう自分の手を、仕方の無いやつだと思ったことはあれど、憎んだ事は無い。
むしろこれは天意に適う事ではないか。美を至高のものとする芸術的観念が著しく顕なはっかい。には、女性が本来有している美を無視し得よう筈など無かった。
ファッション的感覚から見れば、ヌードもまた身体という名の衣服なのである。
薄布一枚であっても、あるいはハイヒール1足だけを身に纏っていても、それは美で在り得るし、でもなければ雑誌の表紙を飾る事も、あるいは展覧会の絵として、世界芸術史上においても特筆され得るべき位置を占めてはいまい。
自分が絵師としてひとえに画道を邁進するのは、秘めたる美を見つけ出し再構築せんが為である。
たとえ『EROろん、EROろん、八休さん』と世に歌われようとも、私は挫けぬ。エロは美だ。エロ・イズ・ビューティフル。
だが、そんな固い決意を、とかく衆目に知らしめようという熱意は在るのだが、要望と収集の度合が過ぎるコレクターが1人、今日もまたはっかい。の心身を痛めつけているのである。
はっかい。とA-Zの眼前に居るのが、その本人であった。
将来性は既に十分保証されている美少年で、とかく人に無理難題を押し付けることで有名なのが水無月であり、一種尊敬を込め『爆弾魔(ボマー)』と称されていた。
無理難題というのも、難癖や罵詈雑言の類などではない。ましてや芸術家である彼らを貶めるなどという忌まれるものではなかった。
『宿題』と他者は言うが、その実、夏休みの課題が質量共に博士論文級に膨れ上がったと見るのが正しい。

端的に言えば、彼からの執筆依頼が引きも切らないのである。
とにかく後から後から連続で畳み込まれる、その口数と依頼の熱意は、力士もおののくがぶり寄りか突っ張りの連続技とも例えられた。
よって水無月の存在そのものを君に君にと押し付けあっているのが、希代の画師、A-Zとはっかいの日常的友情行為なのであった。
「なんだい。また爆弾でも落とされたかね、レジェンド」
「これで通算・・・・・・500、と21個ですの」
ティー・カップをサイドテーブルに置き、はっかいはデッキチェアーへと身を沈め込ませた。
深々と溜息が漏れる。心中には宿題の数が十分な重みを伴って圧し掛かってきていたのだった。
「おや、ようやく500を超えたのかい。てっきり700に手が届くと思っていたが」
「700・・・・・・あと2週間内にはお願いしたいところですの」
鬱々として楽しめぬ空気が、はっかい。の周囲に漂い始めた。
心なしか、しくしくとすすり泣く声までもが漏れ聞こえてくる気がする。
陰鬱さが生じ始めた朝の爽快さを、だが決して失わず、A-Zと水無月は和やかな会話を始めていた。
「頑張れ、レジェンド。未来は明るいぞ」
「あ、そーそー。ししょーにもお願いしなきゃいけなかったですの。頼んでいたタマモンと横島君のイラスト15枚、いつになったら・・・・・・」
無言のままにA-Zは踵を返し、足早にドアへと向かっていた。
後方で振り回し始めた、水無月の投げ縄にも気付かぬまま。
はっかい。が静かに零す、すすり泣きの声を顧みる者もまた居ない。
アトリエ・エイト・シーズの朝はこうして始まる。
To be continued


